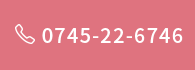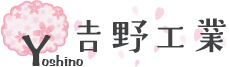4月はイベントや行事がたくさんありますよね。
中でもイースターをご存知でしょうか?
日本ではあまり馴染みのないイベントですが、テーマパークなどでは定着しつつある行事です。
今回はイースターについて解説していきます。
イースターはいつ?
イースター日付けは毎年変わりますが、大体4月中の日曜日というのが決まっています。
基本的には春分の後の、最初の満月の次の日曜日です。
2022年は4月17日(日)がイースターです。
イースターとは?
キリストの復活を最大級の奇跡として弟子たちは喜び、祝ったといいます。
この日は教会で礼拝が行われ、装飾されたイースターエッグが配られます。
その後に、「イースター」という一大イベントになったと考えられています。
代表的なイースターのシンボル
イースターエッグ(復活祭の卵)は、イースターを祝うための特別な鶏卵のことで、
この日にはなくてはならないもの。
もともとはゆで卵を使用していましたが、最近ではチョコレート、ゼリー、砂糖など、
さまざまな食材で作られたものが見受けられます。
もう一つのシンボルが野ウサギ。
イースターバニーと呼ばれ、子どもたちにイースターエッグを運んでくるのがその役割です。
イースターの楽しみ方
草木が萌えいづる庭や森で大人が先に隠しておいたペイントした卵やウサギチョコを子どもたちが探し、
わくわくした気分を楽しみます。
キリスト教が主流の世界の国々では、街のそこかしこで、春の訪れを祝うかのように、
厳かにそして華やかにイースターの祝宴が行われています。
4月は進学や就職、転勤等で新年度を迎え、新しい環境に気持ちも新たにスタートする時期でもあります。
入社式や入学式等の大きなイベントもある出会いの季節。
何かと忙しく、疲れも出やすくなるのでくれぐれもご自愛くださいね。