
桜と同じように、中国から伝わって定着した春の花はほかにもあります。
その中でなぜ、桜だけが日本中で愛されるようになったのかについては諸説ありますが、
おおむね以下のような理由ではないかと考えられています。
・見た目の愛らしさ、美しさ
薄く小さな花びらや、可憐な薄いピンク色など、
純粋に桜の花が持つ美しさに心惹かれた日本人が多かったのは、大きな理由の1つといえるでしょう。
・生死の象徴としての崇拝
桜の木自体の寿命は長く、品種によっては100年以上を誇るものもありますが、桜の花はごく短命です。
春の間でもほんの短い期間だけに咲き誇り、
風と共に薄い花びらはさらさらと散っていくため、見ごろは半月もありません。
美しい桜の花が一瞬咲き乱れ、はかなく散っていくようすを見た古来の人々が、
桜によって死生観に思いを馳せたり「神聖なもの、神を思わせるもの」として、
桜を崇拝の対象にしたりしていたと考えるのは、難しいことではないでしょう。
・開花時期の待ち遠しさ
現在でも、春のお花見シーズンが近づいてくると「桜の開花予想」が全国で報じられ、
いつが見ごろとなるかが注目の的となります。
今より天気予報の発達していなかった時代においても、
桜の木がピンクに色づき、花のつぼみがつきはじめると
「いつ満開になるのか」と待ち遠しい気持ちで桜を見守った人々も多かったことでしょう。
冬から春への移り変わりは、農耕のはじまりや冬の寒さにこごえる日々の終わりを意味します。
こうした期待が、春の訪れを告げる桜の美しさを一層盛り上げる後押しとなっていたとも考えられます。
日本人は古来より桜の美しさ、可憐さに心惹かれ、
また春の訪れを告げる神や精霊が宿る存在と考えられたり、
はかなく散ってゆく命の短さから死生観を考えたりする対象となってきました。
その中でも、樹齢の長いものや枝ぶりの見事なものは「三大桜」として特に大切にされており、
天然記念物や史跡名勝として国からも守られています。


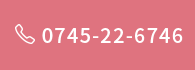
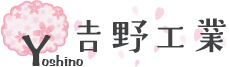
 冬から春にかけて店頭に並び、スイーツの主役やいちご狩りでも大人気の「いちご」。
冬から春にかけて店頭に並び、スイーツの主役やいちご狩りでも大人気の「いちご」。






