2023年07月21日
暑さが厳しくなり、学校でのプール授業も行われています。
暑い日は、ひんやりとしたプールに入りたくなりますが、実は、プールでも熱中症のリスクがあるんです。
なぜ冷たい水の中に入っていて熱中症になるのか。
プールでの熱中症のリスクについて見ていきます。
実は気づきにくいですが、水の中にいるときでも泳いでいると大量に汗をかいています。
環境省によりますと、高校の水泳部の練習では、体重1キロあたり約7.5gの汗をかくということなんです。
ですので、単純に計算すると体重50キロの場合375g、缶ジュース1本分ぐらいの汗をかいているという計算になります。
また、水の中にいると口の中が水で濡れるので、喉の渇きを感じにくくなってしまいます。
軽い脱水症状のときにも、喉の渇きを感じなくなってしまうことがあるので要注意なんです。
学校などではプールサイドはコンクリートのところが多く、日よけもあまりないところが多いです。
水着で露出も多くなっています。
このため、熱や日差しを遮りにくくなり、熱中症のリスクが高くなるということなんです。
水に入ってる時だと「熱は放出されてるはず」と思っているからこそ、要注意ともいえます。
プールでの熱中症対策を改めて見てみます。
運動中は冷たい飲み物
プールに限りませんが、運動中は冷たい飲み物で水分補給するようにしてください。
冷たい飲み物は、脳や臓器など体の内部の温度を下げてくれる効果があります。
頭部を水中で冷やす
体の他の部分と違って、頭部というのは常に直射日光が当たっているような状態になっています。
頭部をときどき水の中に入れて冷やしてあげることが大切です。
風通しの良い日影で休憩
ずっと水の中にいるのではなく、風通しのよい日陰でこまめに休憩をするということも意識的にするようにしてください。
こういったことに気をつけて、プールにいても熱中症に十分気をつけるようにしてください。
もちろんプール以外でも熱中症には十分気を付けて、夏を楽しむ準備をしましょう!



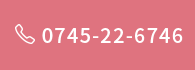
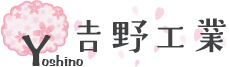







 冬から春にかけて店頭に並び、スイーツの主役やいちご狩りでも大人気の「いちご」。
冬から春にかけて店頭に並び、スイーツの主役やいちご狩りでも大人気の「いちご」。